「合否を分けるのは知識の量じゃない。小数点以下の、精度への執念だ。」
初回の記事でお伝えした、この言葉を覚えていますか?
コンクリート技士試験の合格を掴むために、私たちは今、最も効率的に得点を伸ばせる「5つの計算問題」の攻略という冒険に出ています。
暗記という無限に思える荒波を乗り越える羅針盤。それが、体に染み込ませた「計算力」です。
さて、今日はいよいよ、ラスボスが繰り出す5つの必殺技のうち、最も基本的かつ最重要と言える一つ目の技の攻略法を伝授します。
それは、「配合設計」における「単位水量」と「水セメント比」の計算です。
この計算は、いわば料理における「塩加減と出汁の取り方」。
どんなに高級な食材(知識)を手に入れても、ここを間違えれば、美味しい料理(=安全なコンクリート)は絶対に作れません。
今日の記事を読み終える頃には、あなたは配合設計問題に対する確固たる自信と、具体的な得点力を手に入れているはずです。
■ なぜ、この計算が「最重要」なのか?
コンクリートの品質は、ほぼ「水セメント比」で決まると言っても過言ではありません。
- 強度
- ワーカビリティー(施工のしやすさ)
- 耐久性
これらコンクリートの根幹をなす性能はすべて、セメントに対してどれだけの水を使ったか、という極めてシンプルな指標に支配されています。
試験でこの問題が頻出するのは、「あなたは、コンクリートの最も基本的な性格を理解していますか?」という、技術者としての資質を問うメッセージに他なりません。だからこそ、ここを落とすわけにはいかないのです。
■ 攻略の核心!押さえるべき公式はこれだ
まずは、武器となる公式を確認しましょう。非常にシンプルです。
水セメント比 (%) = (単位水量 ÷ 単位セメント量) × 100
この式を変形すれば、他の数値を求めることもできます。
単位セメント量 = 単位水量 ÷ (水セメント比 / 100)
単位水量 = 単位セメント量 × (水セメント比 / 100)
「単位量」とは、コンクリート1m³あたりに使われる材料の質量(kg)のこと。この基本を絶対に忘れないでください。
■ 「配合設計」問題の解法シミュレーション
では、実際の試験でどう立ち向かうのか。具体的な思考プロセスを見ていきましょう。
【手順①】問題文から「目標スランプ」と「粗骨材の最大寸法」を探せ!
配合設計の問題では、まず「単位水量(W)」を決定する必要があります。
そのための最大のヒントが、この2つのキーワードです。
- スランプ:コンクリートの軟らかさを示す値。
- 粗骨材の最大寸法:使用する砂利の大きさ。
問題用紙に、これらの関係から単位水量を求めるための「表」が与えられているはずです。まずは、その表と問題文の数値を冷静に照らし合わせ、単位水量(W)の基準値を確定させます。
【手順②】「水セメント比(W/C)」を読み取る
次に必要なのが「水セメント比(W/C)」です。
これは、要求される「計画供用期間の級」や「設計基準強度」などから、同じく問題文中の表や条件を読み解いて決定します。
【手順③】公式に代入し、「単位セメント量(C)」を算出する
手順①で「単位水量(W)」が、手順②で「水セメント比(W/C)」が分かりました。
ここまでくれば、あと一息。先ほどの公式に代入して、「単位セメント量(C)」を計算します。
単位セメント量(C) = 単位水量(W) ÷ (水セメント比(W/C) / 100)
これで、解答の主要な要素が出揃いました。
■ ここで差がつく!よくあるミスTOP3
しかし、多くの受験生がこのシンプルなプロセスで失点します。あなたがハマってはいけない「落とし穴」を3つ紹介します。
- 第1位:表の数値をそのまま使ってしまう表に書かれているのは、あくまで「標準的な配合」の場合です。問題文に「高性能AE減水剤を使用し、単位水量を〇kg低減する」といった【補正条件】が書かれていないか、必ず確認してください。この一文を見逃すだけで、答えは全く違ってきます。
- 第2位:単位の勘違い水セメント比は「%」で与えられます。計算に使う際は、必ず「100」で割って小数に戻すこと。この一手間を惜しむと、桁が全く合わなくなります。
- 第3位:問題の要求を読み間違える問われているのは「単位セメント量」なのか、「単位水量」なのか、それとも「水セメント比」なのか。計算に夢中になるあまり、最終的に何を答えるべきかを見失うケースです。計算が終わったら、必ず問題文を再読しましょう。
■ 次回予告
配合設計の心臓部、「単位水量」と「水セメント比」はマスターできたでしょうか。
しかし、ラスボスの攻撃はまだ終わりません。
コンクリートの「骨格」となる材料、骨材。その性質を正確に把握していなければ、どんなに良い配合も絵に描いた餅です。
次回は、多くの受験生が混同しがちな、あの計算問題に切り込みます。
【第3回】これで完璧!「絶乾密度」と「表乾密度」の使い分け
一見すると複雑に見える骨材の計算も、ポイントさえ掴めば確実に得点源に変わります。
この調子で、一つずつ必殺技を打ち破っていきましょう。あなたの合格は、もう目の前です。

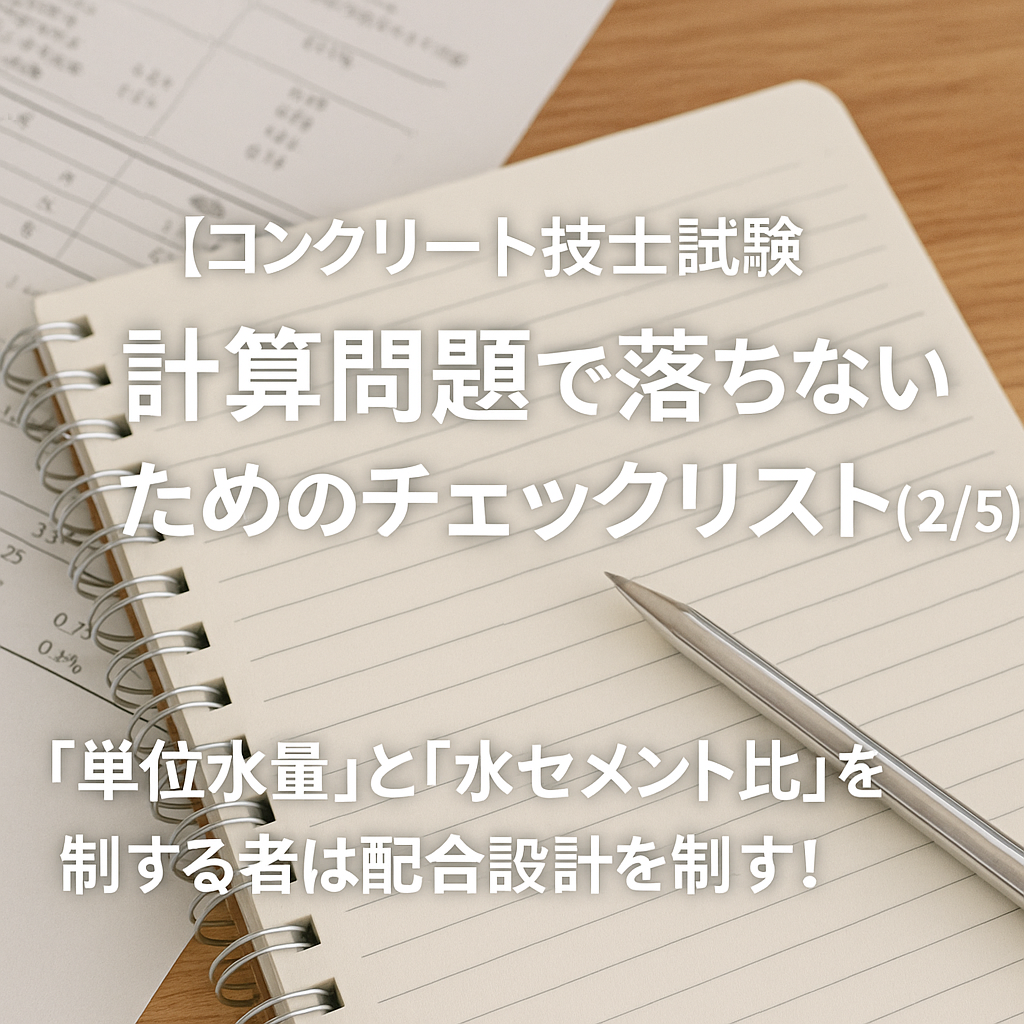
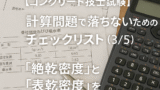
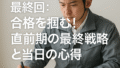
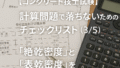
コメント